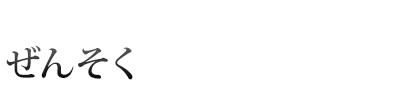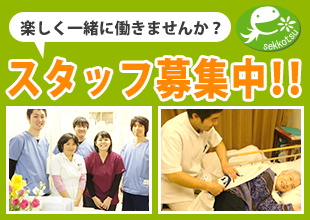ぜんそく(小児ぜんそく)⑤
小児ぜんそくは、著しく増えていて、今日では4歳以下の子どものおよそ7人に一人は、ぜんそく症状があるというわけです。
小児ぜんそく発症のピークは1~2歳で、2歳ごろまでに約60%、6歳までに約90%が発症します。
比較的改善しやすいという特徴があり、中学に入学するころには約70%が寛解するといわれています。
しかし、約30%は成人ぜんそくに移行してしまいます。いったんおさまり、成人する例もあります。
成人ぜんそくとは異なり、小児ぜんそくの90%以上はアトピー型です。
生まれつきのアトピー体質が深く関与しており、家族にアレルギー歴がある場合は、特に発症しやすいので注意が必要です。
子供の気管や気管支は、細い、やわらかい、痰などの分泌物が多い、という特徴があります。
そのため、ちょっとした刺激で気道が狭くなり、喘鳴が起きやすくなっています。
はじめは、ぜんそく様気管支炎と診断されることもあります。かぜをひきやすく、そのたびにちょっとゼーゼーしたり、咳が長引いたり、などの症状を繰り返しているうちに、いつのまにかぜんそくを発症していたという例が多いのです。
小児ぜんそくの根底にあるアトピー体質は、その他のアレルギー疾患も引き起こしがちです。
乳児期にはアトピー性皮膚炎、1~2歳になると、小児ぜんそく、学童期にはアレルギー性鼻炎というのが典型的なパターンです。
このように、成長するにつれて異なるアレルギー疾患が次々にあらわれるのを「アレルギーマーチ」と呼んでいます。
しかし、アトピー体質を持つ子ども全員が、ぜんそくを発症するわけでも、アレルギーマーチを引き起こすわけでもありません。
アレルギー疾患は、生まれつきの体質と環境要因が複雑にからみあって発症します。できるだけ、アレルゲンを取り除き、環境を整えることが大切です。
小児ぜんそくのアレルゲンの90%は、ダニの死がいや糞といわれています。
こまめに部屋の掃除をし、布団もよく日に干して裏表に掃除機をかけましょう。
乳幼児期には、親が子供の様子をよく観察し、いつもと違う様子が見えたら早めに受診しましょう。
赤ちゃんの気道は狭いため、急速に悪化することがあるので注意が必要です。
ぜんそくはどういう病気なのか、どんなときに起こりやすいか、どんな前触れがあるのか、発作が起こったらどうしたらいいか、すこしずつ子供に教えていくことが大切です。
子どもには理解が難しいと感じても、根気よく丁寧に説明することも大切です。
適切な対応をすれば、発作をコントロールできることがわかれば、子どもも安心できるはずです。
学校にも、ぜんそくを持っていることや、発作がおこったときの対応なども伝えておくことも大切なことです。