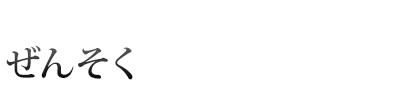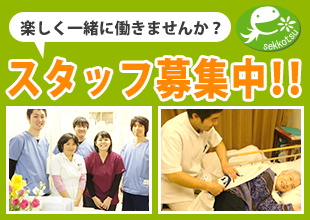ぜんそく(発作の特徴)②
起こりやすい時間帯
ぜんそく発作にはいろいろな特徴があります。第一の特徴は、発作は深夜から明け方にかけてのおもに就寝中に起こりやすいということです。
横になって寝ているより座っているほうが呼吸をしやすいので、体を起こして発作がおさまるのを待つ人も多いようです。これを「起坐呼吸」といいます。
この時間帯に起こりやすい理由として、次のようなことが考えらます。
自律神経のバランス
就寝中は、交感神経より副交感神経が優位になります。
副交感神経には気管支を収縮させる作用があるので、発作が起こりやすくなります。
明け方の冷え込み
明け方4~5時ごろは急激に気温が低下します。その刺激を受けて気管支が収縮するため、発作が起こりやすくなります。
分泌物がたまる
気管支からは絶えず粘液が分泌されており、日中は無意識に飲み込んだり、吐き出したりしています。
しかし、就寝中は気管支の中にたまるので、この刺激によって発作が起こりやすくなります。
血中カテコールアミンや、コルチゾールの低下
気管支を広げたり、炎症を抑えたりする働きのある体内物質が少なくなっています。

発作は安静時にも起こる
運動したり、坂道や階段を上ったりするなど、ふだんより激しく体を動かすと、息切れして呼吸がしにくくなります。
運動時にはより多くの酸素が必要となるのに、COPDでは酸素を十分に取り込めないため、酸素不足になって呼吸困難に陥るのです。
これは、「労作性の呼吸困難」と呼ばれています。
一方、ぜんそくの発作は、特別なことを何もしていなくても起こります。
前述のように、安静にして横になっているときにも発作が起こるのは、ぜんそくの大きな特徴といえるでしょう。
ぜんそく発作は一時的ですが、繰り返し起こります。発作時は非常に苦しいので病院にかけ込んだり、しばらくは用心したりします。
しかし、いったんおさまると、ふだんと変わりなく活動できるため、油断してしまうのです。
忙しさや面倒くささも加わって、自己判断で治療をやめたり、管理がいいかげんになったりしがちです。
しかし、気管支の炎症はなくなっていません。
気道が敏感な状態もよくなっていません。
なにかの刺激で再び発作が起き、さらに発作が炎症を悪化させるという悪循環に陥ってしまうのです。
もちろん気道はさらに敏感になってしまいます。
ぜんそくの発作は、季節や気候とも関係があり、春や秋など、季節の変わり目に起こりやすいといわれています。
春や秋は日々の寒暖の差が大きいうえ、1日のうちでも朝晩の冷え込みが強く日中との温度差が大きくなります。
このような急激な温度変化が、発作を誘発すると考えられています。
また、移動性高気圧や台風が近づいたとき、寒冷前線が通過する時期など、気圧が急変するときも、発作が起こりやすくなっています。
梅雨の時期も湿度が高くなり、アレルゲンとなりやすいカビやダニが多く発生するので注意が必要です。