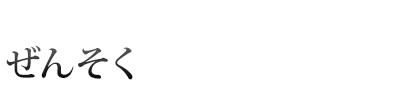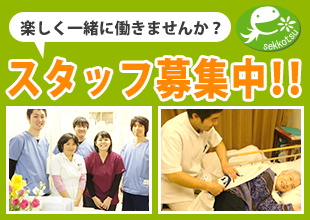ぜんそく(タイプとメカニズム)④
ぜんそくにはアトピー型と非アトピー型があります。
アトピー型は、特定のアレルゲン(抗原)が引き金になって起こるものです。
アレルゲンには、食物アレルゲン、吸入アレルゲンなどがあり、ぜんそくは、主に吸入アレルゲンによって引き起こされます。
もっともアレルゲンとなりやすいのはダニです。カビ、ペットの毛やフケなども要注意です。
このようなアレルゲンを空気と一緒に吸い込むことによって、気道の粘膜にアレルギー反応が起こるのです。
ぜんそくの多くはこのアトピー型で、成人の患者さんの約60%、子供の患者さんの90%を占めます。
非アトピー型の誘引のトップは、ウイルス感染によるものです。アトピー型のように原因を特定することは困難です。
また、意外に思われるかもしれませんが、最近の研究によって、非アトピー型は肥満とも深い関係があることがわかってきました。
肥満度が高くなるほど、ぜんそくの発症リスクが高まり、重症度とも関係があります。
特に女性ではその傾向が顕著で、逆にいうと、こうした場合では減量によりぜんそくを改善できると考えることができます。
アトピー型も非アトピー型も発作の引き金になる刺激はさまざまで、かぜやインフルエンザなどの感染症、たばこの煙や排気ガス、化粧品や香水、気温や湿度の変化、冷気、ストレス、過労、食品添加物、薬などが挙げられます。
アトピー型の発作は2段階あり、アレルゲンを吸入して数分から30分前後であらわれるものを「即時型反応」、3~6時間後にあらわれるものを「遅発型反応」といいます。これらの2つの反応が関連しながらくり返し起こるうちに炎症が進行し、症状が悪化していきます。
アレルゲン(抗原)が気道に侵入すると免疫システムが働き、まずマクロファージが出勤してアレルゲンを食べ、敵の情報をヘルパーT細胞に伝えます。
ヘルパーT細胞は司令官の役目をしており、B細胞にIgE抗体をつくれ、と指示します。
それを受けて、B細胞はIgE抗体を大量に産生し、アレルゲンを攻撃します。
このとき過剰につくられたIgE抗体がマスト細胞にくっつき、次の侵入に備えて待機します。
再度同じアレルゲンが侵入すると、アレルゲンはマスト細胞に付着しているIgE抗体と結合します。これが抗原抗体反応です。この刺激で、マスト細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出されます。
どちらにも気管支を収縮させたり粘膜をむくませる作用があるため、より気道が狭くなり、発作が起きます。ここまでが、第一段階の即時型反応です。
一方、遅発型反応の主役となるのは「好酸球」です。
即時型反応がおさまってほっとした頃、マスト細胞から放出された好酸球遊走因子やヘルパーT細胞が産生したサイトカインなどによって、今度は好酸球が大量に気道に集まってきます。好酸球は、ロイコトリエンなどの化学伝達物質のほか、MBPやECPというたんぱく質を放出します。これらのたんぱく質には、体の組織を破壊する性質があり、気道の粘膜上皮を傷つけてはがしてしまうのです。 このため、上皮の下の神経がむき出しになり、気道の過敏性が増し、発作がおこりやすくなります。
成人では、小児に比べるとアトピー型の割合が減少し、非アトピー型の割合が多くなっています。とくにかぜをはじめとするウイルス感染が、大きな要因の一つであるのはまちがいありません。 外部からウイルスが侵入すると、直ちに免疫システムが作動し、先兵隊の好中球とマクロファージが食べて殺します。ナチュラルキラー細胞も駆けつけてウイルスを攻撃します。
こうして戦いながら、「もっと応援隊を送れ」という指令を飛ばします。 これに呼応して、どっと集まってくるのが好酸球です。アトピー型の遅発型反応と同じで、好酸球が出勤して大暴れし、ウイルスだけでなく、気道の粘膜までも破壊してしまうのです。
このため、気道が非常に敏感になり、ちょっとした刺激にも反応して発作が起こりやすくなります。このように、好酸球は、アトピー型にも非アトピー型にも深く関与していることがわかっており、ぜんそくは別名「慢性剥離性好酸球性気管支炎」とも呼ばれています。やっかいなことに、好酸球による炎症は、長引きやすく、慢性化しやすいという特徴があります。できるだけ、好酸球に働くチャンスを与えないことが大切です。
かぜやインフルエンザの流行期には、手洗い、うがいなどを励行し、感染しないように十分に注意することが大切です。