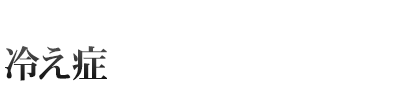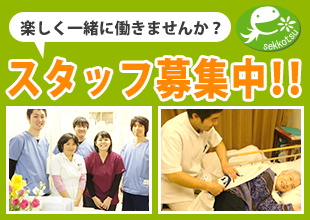冷え症③
人間の体には本来、「ホメオスタシス」(生体の恒常性)を保つように働く機能が備わっています。
自律神経系がバランスよく働くことで体の恒常性が保たれているのです。
私たちが37度前後の体温を維持できているのは、体温調節している自律神経系のおかげです。
自律神経には交感神経系と副交感神経系とがあり、呼吸、血圧、発汗、消化、排尿、排便など、体中の機能を活発にしたり抑えたりして、生命を維持しています。
交感神経は血管を収縮して血圧を上昇させ、副交感神経が働くことで血管を拡張させて血圧を下げます。 こうして二つが連絡しあって働くとき、体の調節はうまくいき、連絡がうまくいかないときには不調になります。
この調節は、眠っている間も、意識せずとも行われるので「自律神経」と呼ばれます。
外気温が下がり寒くなると、皮膚にあるセンサーは、この情報をキャッチして脳(視床下部)にある体温調節中枢に伝えます。
これをうけて体温調節中枢は、体内で作られる熱の量や放出する量を調整します。
また、脳は体から熱が放射する量を少なくするため、交感神経を働かせて血管を縮める指令を出します。
気温が高くなり熱が体内にこもるようになると、副交感神経を働かせて血管を広げ、熱を外へ逃がす指令を出します。
このように、脳に情報を運び、脳からの指令を伝えて臓器や血管を働かせているのが自律神経です。
自律神経は、体中にはりめぐらされたコードのようなもので、交感神経と副交感神経が連携して体の機能を調節していますが、冷えに長年刺さられ続けていると、この連携に乱れが生じ、その結果、広汎に自律神経の不調による症状があらわれるのです。
また、最近訴えが多いのが、緊張性の冷えです。
冷え症は昔からあったものですが、緊張性の冷えは、現代を反映するような新しいタイプの冷えといえます。
冷えはストレスと深い関係があり、自律神経の司令塔である視床下部にはストレスを認知する部分でもあります。
ですから、脳という装置のなかでは体の働きと心の働きが、お互いに影響されやすく、自律神経の乱れはいわゆる自立神経失調状態となります。
自立神経失調になりやすいのは、どちらかというと、内気で几帳面で、神経質な人、ストレスを感じやすく心配事を背負い込みがちです。
おふろにでもゆっくり入ってリラックスできればいいのですが、リラックスするのがへたな傾向があります。
ストレスは交感神経を優位にし、体を緊張させて、体を冷やす最大の要因にもなるのです。
現代人は、皆どこかでストレスをかかえています。言ってみれば、全員が冷え症予備軍ともいえるのです。