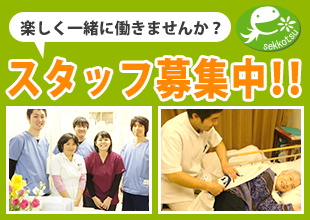そろそろ相続対策②
石田さんのご自宅の評価額は、約6000万円(固定資産税課税明細書より試算)、保有している金融資産は約7000万円です。まずは、相続税の概要ですが石田さんの法定相続人は妻と長男、長女の3人になります。
基礎控除額は≪3000万円+600万円×相続人3人≫で4800万円です。
金融資産だけでも基礎控除を超えること、また、配偶者の税額軽減や自宅について小規模宅地等の特例という軽減措置があることがわかりました。
そして、相続対策の必要性が重要だと気づいた石田さんは相続について考えるうえで重要なのは相続税のことだけでなく、遺産分割も併せて考えていかないとならないことがわかってきました。
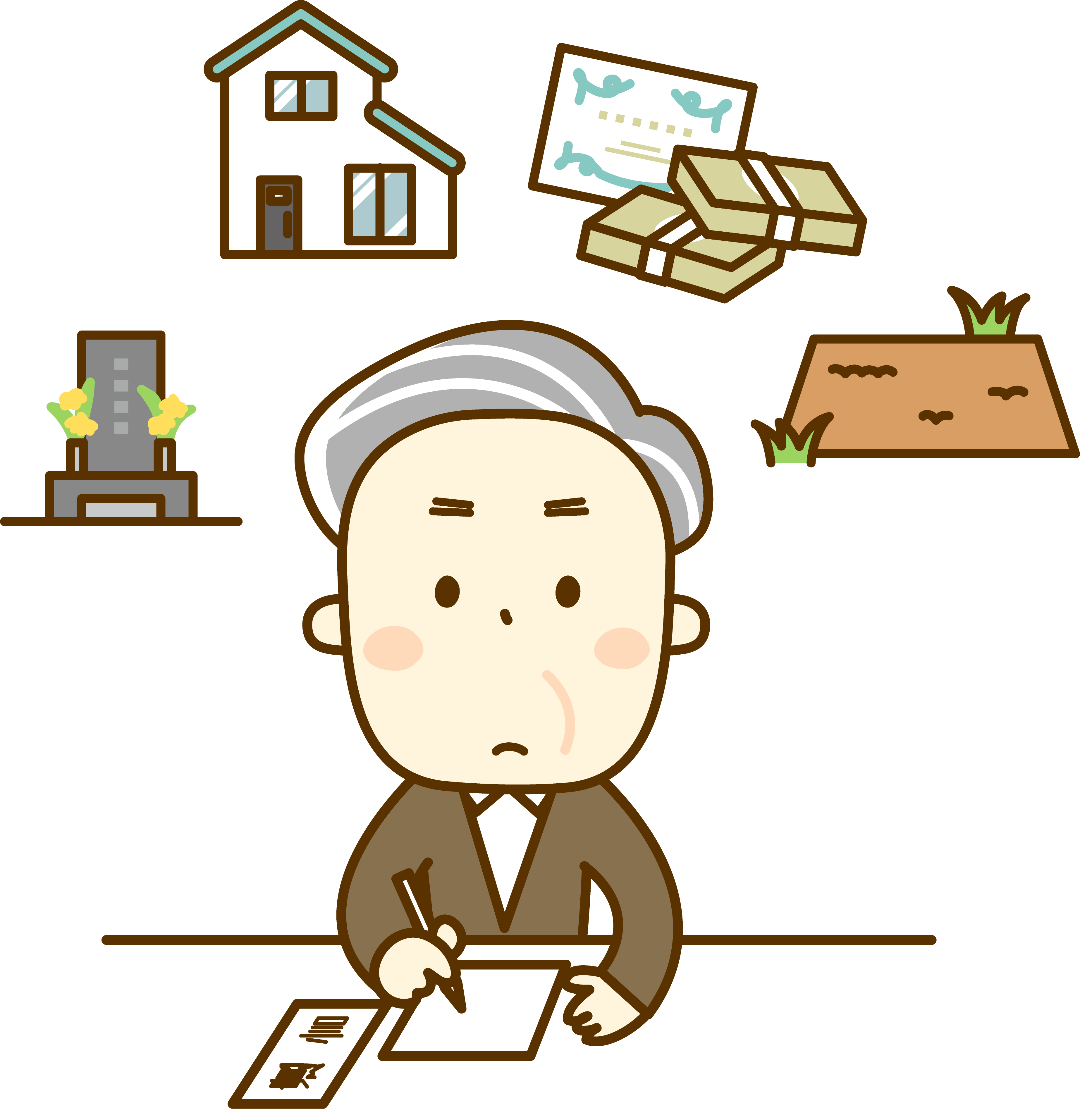
相続税と遺産の分割について
| 相続税について | 遺産分割について |
| ●生命保険の活用 納税資金準備と死亡保険金非課税枠の活用など 自身の年齢で加入できる商品の確認 |
●遺言書の活用 自分の意思に加え、家族が揉めないように分割できるか |
| ●不動産購入で評価額を圧縮 現金で不動産購入など現金資産に十分な余裕があるか |
●一次相続・二次相続 一次相続で相続税負担を軽減することで、 二次相続で税負担が重くなりすぎることはないか |
| ●生前贈与 教育資金贈与の特例の活用など自身の生活費はショートしないか |
相続というと相続税をどう軽減させるかに関心が寄せがちですが、そのためには賃貸住宅を建てたが金融資産が不足して高齢者施設の入居金が用意できなくなったり、現金が残っていないので相続資産の分割ができなくなったり、という事態に陥ってしまうケースも見受けられます。
一方では、相続人が争うことがないよう、分割のことばかりに意識が向き、相続税に関する対策を一切していない、という事例もあります。
石田さんの場合も、相続税と遺産分割の両方への対応をバランスよく考える必要があります。
相続税については、相続人一人当たり500万円が非課税と生命保険の死亡保険金の活用が考えられますが、石田さんの年齢や利回りの低さから、適した保険商品は見つかりにくい状況です。
また、不動産購入や生前贈与については、自宅のリフォーム費用、介護費用など、ご自身の生活費が不足しないかを十分に検討する必要があります。
遺産相続については一次相続だけではなく、二次相続も視野に入れることが重要です。
石田さんの死亡時には、石田さんの妻は、相続財産の2分の1(法定相続分相当額)まで相続しても、配偶者の税額軽減により結果的に相続税がかかりません。この制度を利用して妻が多く相続することを考えがちですが、その場合、妻が多くの資産を持つことになり、妻が亡くなった際の相続(二次相続)が問題になります。
二次相続では法定相続人が長男、長女の2人だけとなり、基礎控除額は≪3000万円+600万円×2人≫で4200万円と小さくなります。
石田さんの場合も一次相続の負担軽減だけを優先させるのではなく、二次相続を踏まえて遺産分割を考えるようにしました。