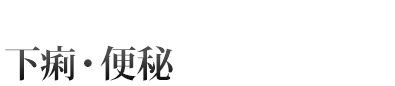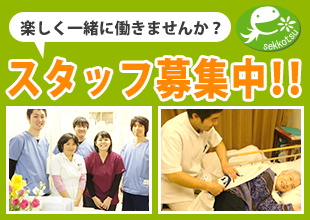- 整腸(消化管のしくみ)①
- 整腸(腸の免疫機能)②
- 整腸(腸は第二の脳)③
- 整腸(腸と臓器の連携)④
- 整腸(排便のメカニズム)⑤
- 整腸(便秘)⑥
- 整腸(腹部マッサージ)⑦
- 整腸(効果的なツボ押し)⑧
- 整腸(効果的なツボ押し)⑨
整腸(腸の免疫機能)②
整腸のことを理解するには、腸のことをよく知らなければなりません。
腸には消化、吸収、排泄の機能があります。老廃物を体外に出す排泄は一種の解毒作用といえますが、腸にはそれ以上の免疫作用があるのです。
腸管免疫といって、ウイルスや細菌などの病原菌を退治する機能です。
全身のリンパ球のうち、実に60%以上が腸管に集中しており、さらに抗体も全体の60%以上が腸管で作られています。
このように、腸は人体最大の免疫器官ですが、なぜ腸がこのような役割を担っているのかというと、それは腸が体の入り口だからです。
口から食べ物を食べたときには、体に取り込んだようでも、実際は吸収されているわけではありません。胃や十二指腸などで消化され、小腸で吸収されたときに、初めて、体内に取り込んだといえるのです。そんな体の入り口である腸に、多くの免疫細胞を配置するというのは必然的です。
腸は入り口で病原菌の侵入を防ぐ、いわば「門番」のような役割を担っているのです。
この腸管免疫の働きを左右するのは腸内細菌です。
腸内細菌は、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌、ウェルシュなどの悪玉菌、どちらでもない日和見菌の3種類があります。健康な状態では、これらの割合は、2:1:7になっています。このバランスが保たれることで、腸管免疫はうまく作用するのです。免疫機能が弱すぎれば、インフルエンザなどの感染症にかかりやすく、ガン細胞も活発になりやすいです。反対に免疫機能が強すぎれば、アレルギー反応が現れます。
健康な人の腸内には約100~1000兆匹の腸内細菌がいます。
想像もつかない数ですが、腸内細菌のほとんどは大腸にいます。大腸の中は腸液や内容物が常に流れていますが、大腸には腸壁に沿って粘液層と呼ばれる厚さ0.1ミリ程度の層があります。腸内細菌はこの中にいるので、流されずに大腸に定着することができます。
腸内細菌は群れを作って生息しており、この群れのことを腸内フローラ、もしくは腸内細菌叢と呼びます。
腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3つのグループがあり、善玉菌は、体によい働きをしてくれる菌で、腸内で発酵を起こします。一方、悪玉菌は体に悪影響を与える菌で、代表的なものとして、ウェルシュ菌、ディフィシール菌などがあり、腸内で腐敗を起こします。
悪玉菌により硫化水素、アンモニア、インドール、スカトールなどの有害物質が発生すると、悪臭や病気の原因となります。
腸内細菌のうち日和見菌が最も多く、全体の70%を占めます。
日和見菌は善玉菌、悪玉菌のうち勢力が強い方の味方をします。体が健康なときは善玉菌が多く、日和見菌は善玉菌に協力してくれます。
しかし、食生活や生活習慣の乱れが続き、悪玉菌が増えてしまうと、日和見菌は悪玉菌に協力するようになり、体調が悪化していきます。
そして、悪玉菌が優位になっていると便秘を起こしやすくなります。
腸内細菌のバランスを整えることは、体を健康にするとともに、便秘解消のためにも重要です。