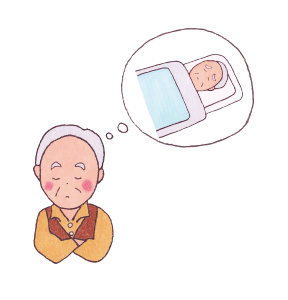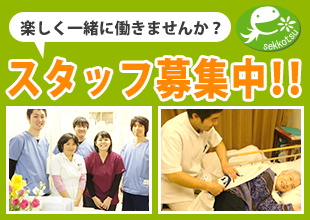関節拘縮とは②
関節とは、運動できるように骨と骨とが連結している部分のことをいいます。
しかし、骨と骨とは硬いもの同士なので、直接触れ合うとお互いの硬さで骨がすり減ってしまいます。
私たちの体を動かすうえで大切な関節は、繰り返しの運動でも骨がすり減らないように、または運動がスムーズに行えるように便利良くつくられています。
例えば、骨同士が直接触れないように、骨の端は「関節軟骨」というスポンジのようなものでおおわれています。
関節軟骨は、水分を多く含み、骨と骨との摩擦を少なくする働きがあります。
また、「関節包」という膜で関節全体を包み込み、「靭帯」と一緒になって骨同士がはずれないように補強をしています。
関節包の内側から分泌される「滑液」は、潤滑油としての働きや、関節軟骨に栄養を送る役割をもっています。

では、関節はどのくらいの期間動かさない状態が続くと拘縮が起きるのしょうか。
動物実験などの研究結果では、2~3日で組織に変化が起こり始めるといわれています。
つまり、たった2~3日で拘縮は起こり始めるということになります。
動かさないために血流の流れが悪くなり、関節やその周囲への十分な栄養を送ることができなくなってしまうことが拘縮の主な始まり方です。
関節の周りにある皮膚や筋肉などは硬く、伸びにくくなり、少しずつ関節が動きにくくなっていきます。
その他にも、痛みなどが原因で、力んでしまって筋肉が収縮しているために、関節が動きにくい場合や、認知症などのためにリラックスしにくく、関節の動く範囲が一時的に狭くなっている場合なども、拘縮とはとらえてないようです。
特に初めの1か月間は変化が大きく、3~4週間動かさない状態が続くと、拘縮はほぼ完成するといわれています。
それ以降も動かさないでいると、関節軟骨も硬く薄くなり、骨と骨との隙間が狭くなってしまいます。
関節はますます動かなくなり、この状態(強直)になると運動での改善が難しくなってきます。
ただし、訪問マッサージでケアすることで、こういったことに対処することも可能ではあります。
できる限り、早めの施術をうけていただければと考えています。